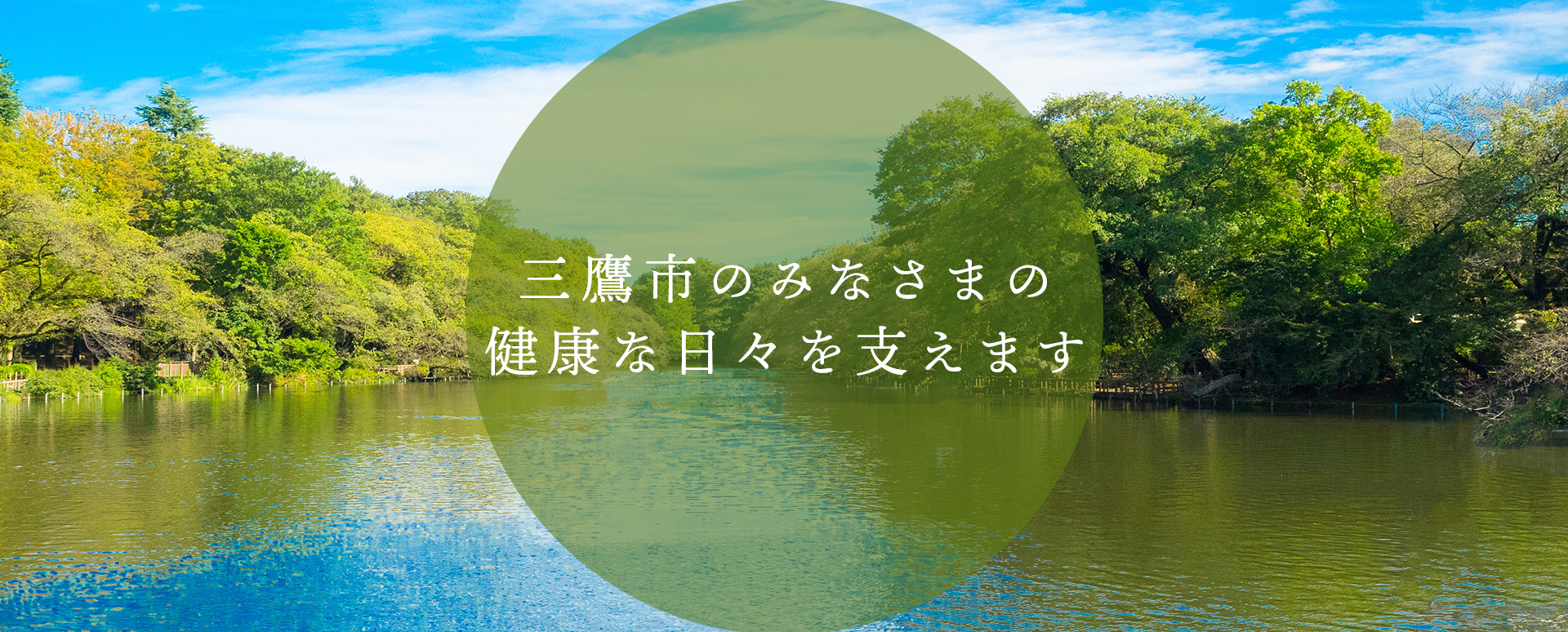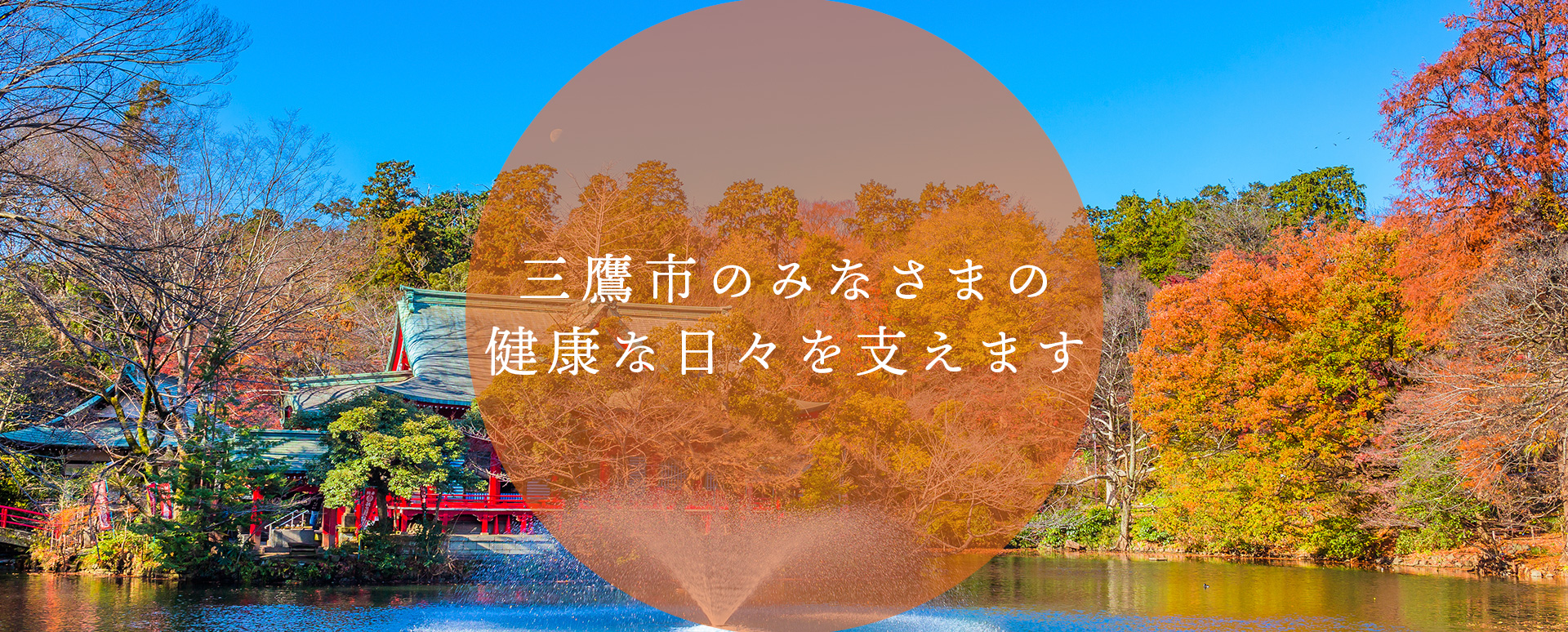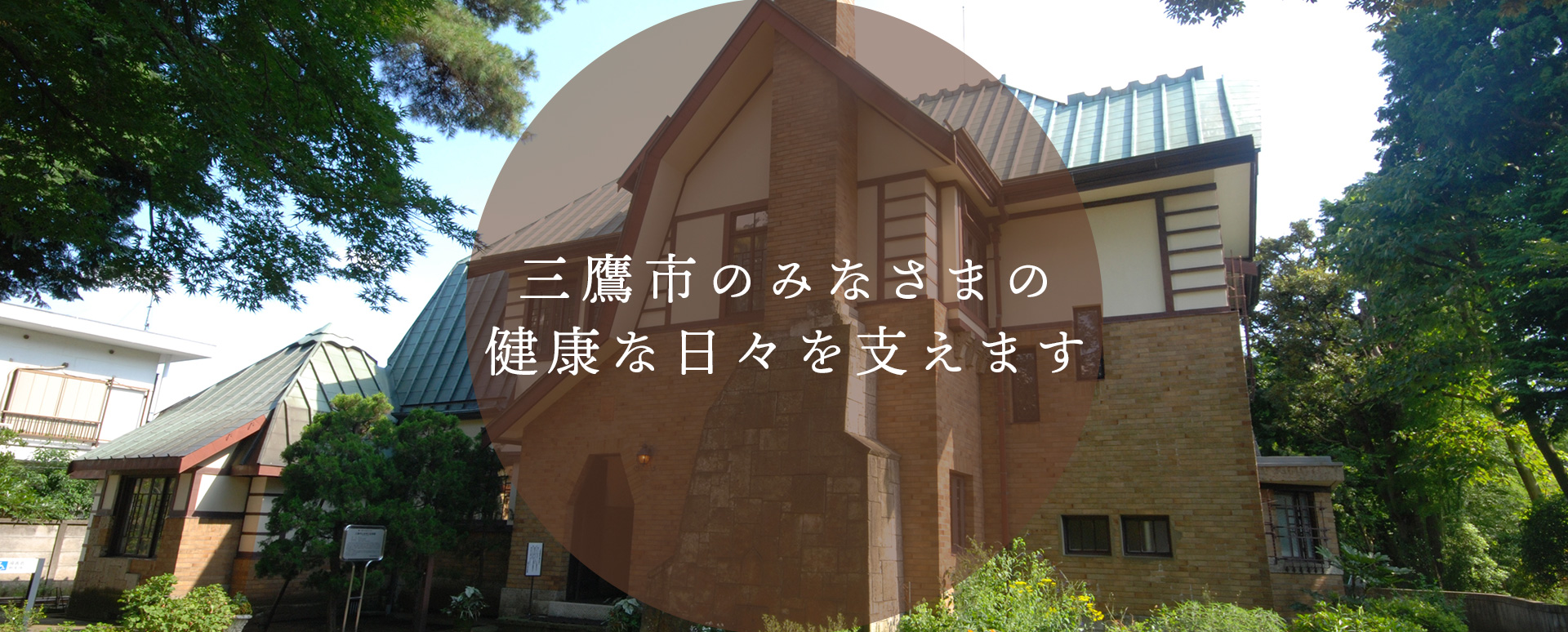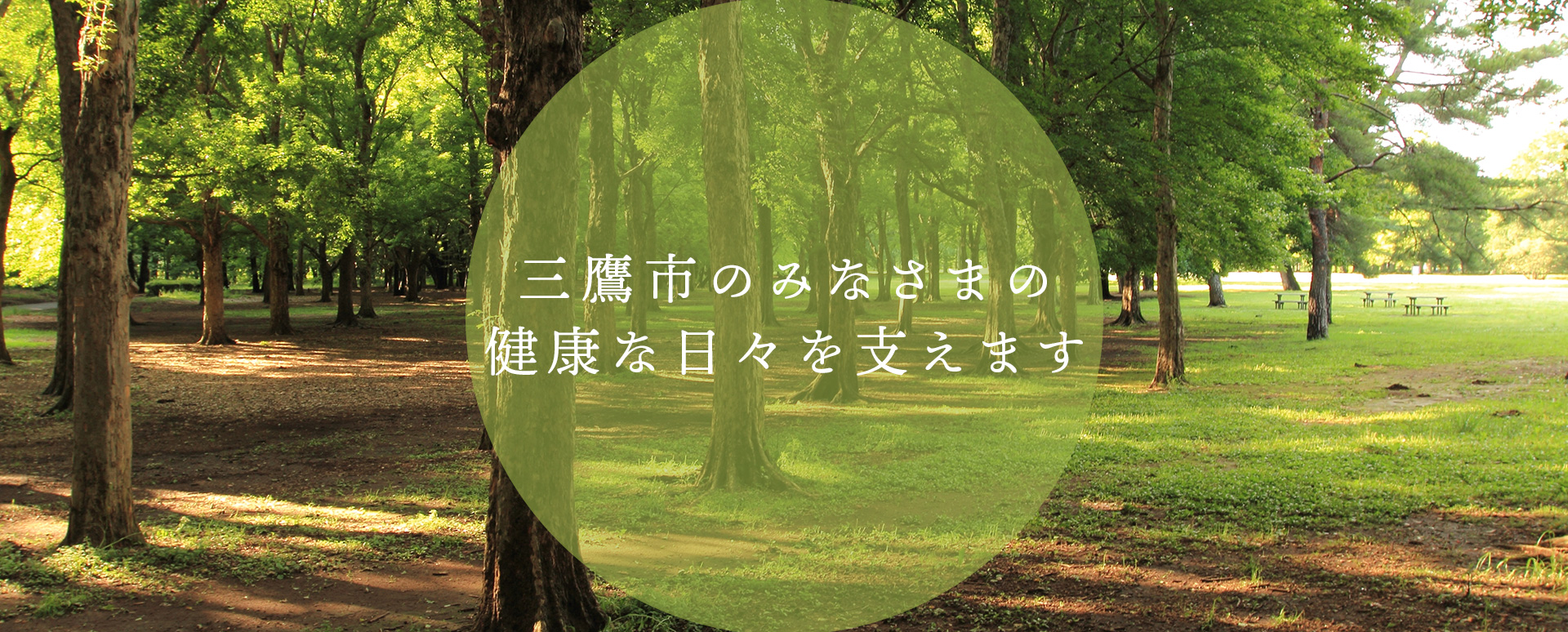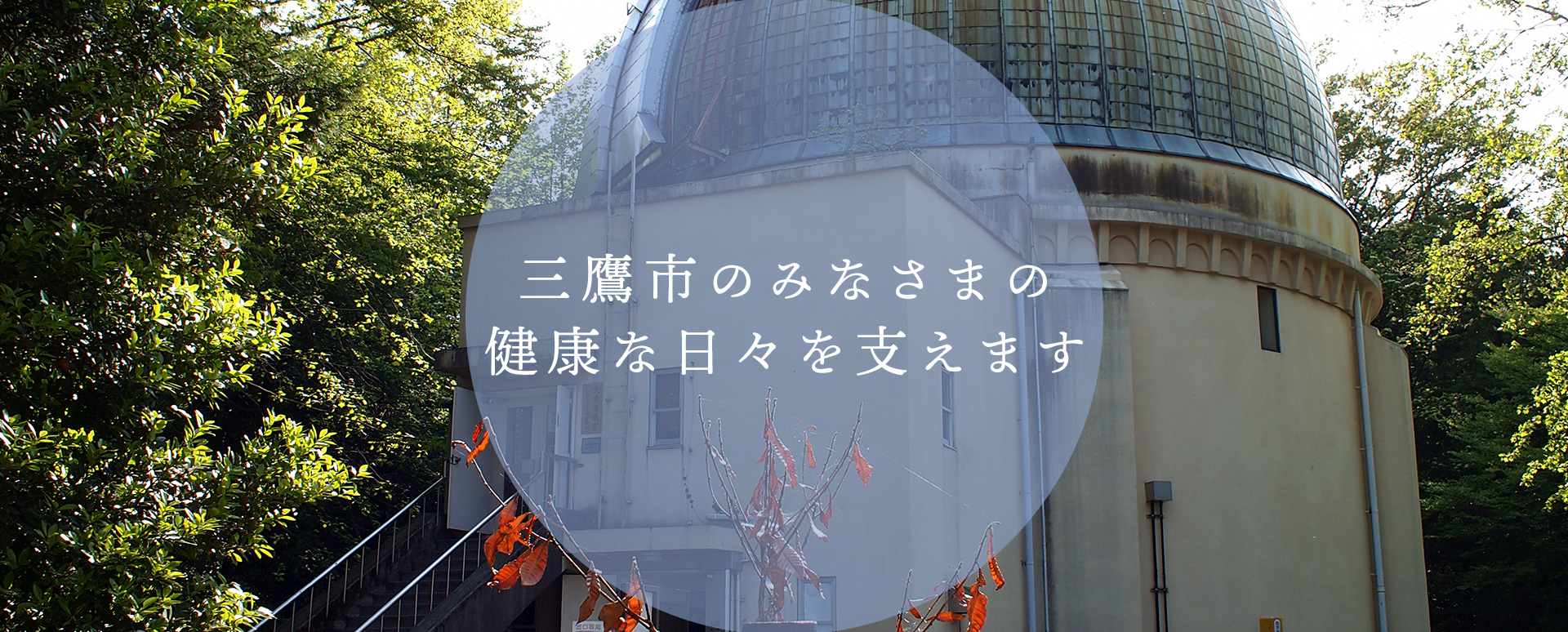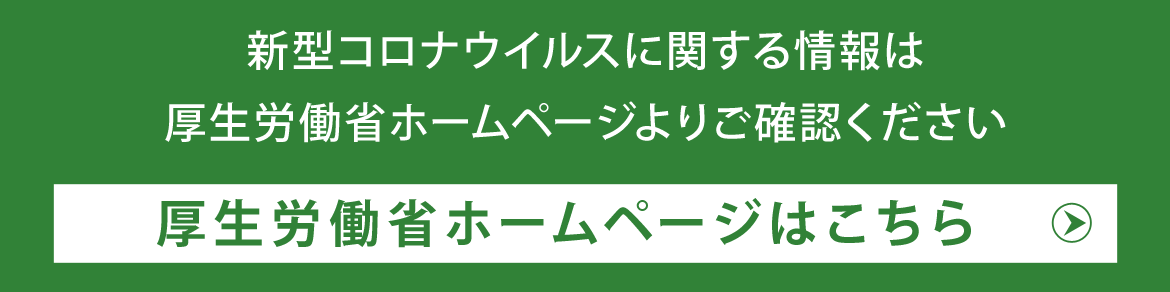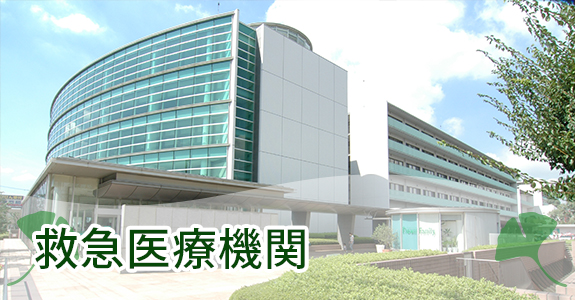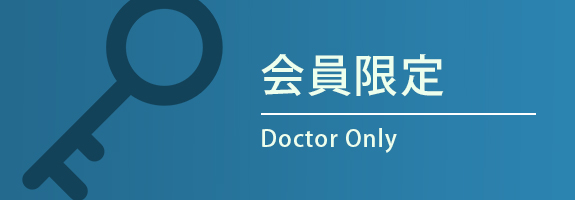公益社団法人三鷹市医師会より重要なお知らせ 令和5年3月5日より休日診療所および小児平日準夜間診療所は 三鷹市休日・夜間 診療所・薬局(住所:三鷹市新川6-35-28)へ移転いたしました。 地図はこちらをクリック 電話番号は「0422-24-6540」となります。 *マイナカードの利用が可能になりました。お手数ですが、保険証のご持参もお忘れなく。 |
三鷹市医師会休日診療所よりお知らせ 感染症の流行等により休日診療所の混雑が予想されます そのため、待ち時間が長時間になる可能性がございます。予めご了承ください。 ご不便をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。 診療受付時間:午前10:00~11:45 午後1:00〜4:30 午後6:00〜9:30 なお、病気に関するご相談は東京消防庁#7119または子どもの健康相談室#8000(03-5285-8898)、こどもの救急(ONLINE-QQ)www.kodomo-qq.jpに 問い合わせおよび検索をして下さい。 また、インフルエンザ、コロナの迅速検査は発熱後すぐでは正確な結果がでないことが多いため、発熱後半日程度経過してからの検査をお勧めします。 休日診療所のご利用にあたって 1,
急病の初期治療を行います。点滴、血液検査は行っておりません。 2,
切り傷、骨折、やけどなどの外科的処置は行えません。市内救急指定病院(三鷹中央病院、野村病院、杏林大学医学部付属病院)などにご相談ください。 3, お子さんの診察に関して、必ず小児科専門医が診察するとは限りません 4, 健康保険証、各種医療証、お薬手帳をお持ちください。支払いは現金、又はクレジットカード等の電子決済をご利用いただけます。 5,
薬は原則、1~2日分の処方となります。
6,
午前の診療が長引いた場合、13時からの診療開始時間を遅らせる場合もあります。又、1日に診療可能な患者数に限りがあるため、患者多数の場合、やむを得ず緊急度の高い方の診療を優先させていただく場合があります。ご了承ください。 |
三鷹市医師会は昭和21年の発足以来、
地域の皆様に健康でより良い生活を過ごしていただくことを目指し
活動を行ってまいりました。
三鷹の発展を担ってこられた世代の方には、医療・介護の充実を。
未来を支える小さなお子様をもつ若い世代には、子育てをしやすい医療環境を。
さまざまな世代が、安心して暮らせる、
「ずっと住みたいまち、三鷹」
の地域づくりを医療を通して支えます。
三鷹市 医療情報
お知らせ
2023/9/8 新着情報
2023/6/29 新着情報
2019/3/1 新着情報
ホームページをリニューアルしました
三鷹市医師会 休日・小児平日準夜間診療所
困った時の相談先はこちら |
消防庁救急相談センター #7119 小児科学会小児救急相談 #8000 |
三鷹市医師会 診療所 Tel. 0422-24-6540 |
定期健診・予防接種

各種検診、予防接種情報は、下記のリンクから三鷹市のホームページをご覧ください。
予防に関するQ&Aについては、感染症情報センターのページをご覧ください。